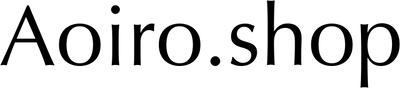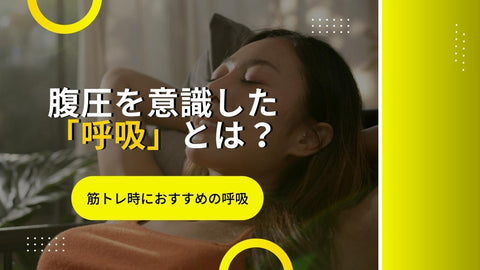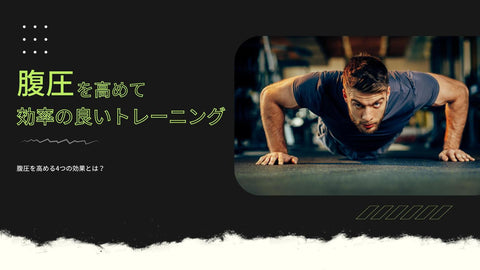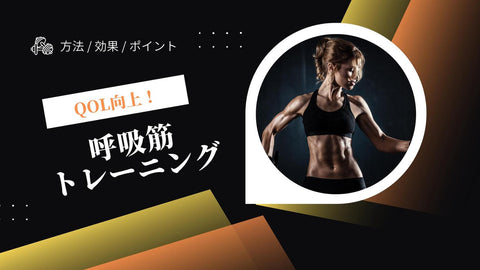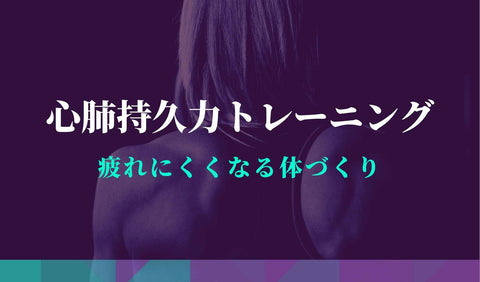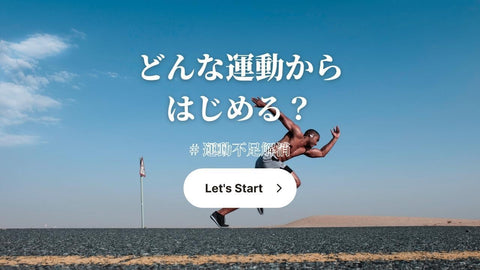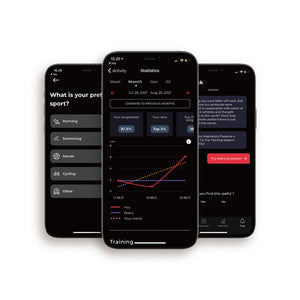健康な生活を送っている人は、日常で肺活量の重要性について考える機会というのはほとんどないと言っても良いでしょう。
しかし、部活で吹奏楽や合唱をしている人にとって、肺活量の有無は音色や声の美しさに直結します。
そのため、吹奏楽部や合唱部の人はいつも「肺を鍛えて、肺活量を増やしたい」と思っているのではないでしょうか。
今回の記事はそんな人のために、肺活量を効率的に鍛える方法をご紹介します。
楽器を演奏するには、肺活量が重要

楽器を演奏する人、特に吹奏楽で楽器を演奏する人にとって、肺活量の増減は死活問題と言っても良いかもしれません。
特に中学校・高校の吹奏楽部の人の中には、体育会系の部活と同じくらい厳しいトレーニングをしている人も少なくありません。
ここでは吹奏楽をしている人にとって、なぜ肺活量が重要なのかを改めて考えてみましょう。
① 木管・金管楽器にとって、呼吸は音の主要材料
吹奏楽の場合、楽団を形成する主要な楽器は金管楽器・木管楽器・パーカッションの3種類です。
この中でも、金管楽器と木管楽器の場合は、音を出すには楽器に空気を入れる必要があります。
いわば、人間の呼吸が楽器の音色の原料なのです。そのため、演奏者の肺活量が楽器の音色に直結します。
実は、木管楽器と金管楽器を分ける基準も、この息の入れ方の違いによるものです。
唇にマウスピース(リード)を入れて音を出す楽器が金管楽器(トランペット・ホルン・トロンボーン・チューバ等)、楽器に直接唇をあてて音を出す楽器を木管楽器(サックス・フルート・クラリネット・オーボエ等)と呼びます。
そして、金管楽器では楽器の大きさが必要な肺活量に比例します。つまり、大きな楽器ほど沢山の肺活量が’必要になります。よって、トランペット→ホルン→トロンボーン→チューバの順で沢山の肺活量が必要になります。
一方、木管楽器では、クラリネット→サックス→フルートの順に多くの肺活量が必要になります。見た目が細くて可憐な音を出すことができるフルートが、サックスよりも多くの肺活量が必要であることに驚く人も多いことでしょう。しかし、実際に特にフルートを担当する人は、女性であっても吹奏楽の楽器の中でもトップクラスの肺活量を持っていたりするのです。
このように金管・木管楽器にとって、肺活量の有無は楽器の音を左右する重要な問題なのです。
② パーカッションにとっても、力を入れる時に呼吸は大事
金管楽器と木管楽器をする人にとって肺活量が重要であることは、すでに述べました。一方、意外なことですが、パーカッション担当の人にも肺活量は大事なのものなのです。
パーカション担当の人は演奏中、常に緊張して自分が音を出す瞬間を待つことになります。
人間は緊張すると呼吸が浅くなり、体内に酸素が行き渡りにくくなります。そのため、体内に酸素が少なくなると、音を出す瞬間に適切な力を出すことが難しくなります。
しかし、肺活量がアップすると、自分の緊張がコントロールできるようになり、力を出すべき瞬間に必要な力が出しやすくなる可能性があります。
合唱部の人も肺活量を増やすことは重要
吹奏楽をする人だけでなく、合唱をする人にとっても、肺活量を増やすことは重要なことです。では、合唱部の人にとって、肺活量のUPはどのような影響を与えるのでしょうか。
声を出すためには肺活量が不可欠
人間の声が生み出されるのは、喉にある「声帯」という小さな2本の筋肉です。この間を空気が通り抜けることで音が初めて出て、その音が「声」と呼ばれるようになります。
人間は呼吸するとき、息を吸うか吐き出すか、どちらか一方の動作をしています。そのため声帯には吸った空気と吐いた空気の両方が通り抜けますが、吐いた空気が声帯を通過したときだけ「声」が発生します。つまり、声を出すには、息を吐き出す必要があるのです。
人が歌うときもこのことは同じです。つまり、人間は息を吐き出さないと歌うことはできません。そのため、肺活量がまったくないと「声」を出せないということになり、歌も歌えないということになるのです。
ちなみに、金管・木管楽器は演奏時には人間が息を吐き出して音を出しますが、ハーモニカなどは息を吸うことでも音を出すことができます。
つまり、声を出すためには息を吐き出すことが必要になります。合唱の人は息を吐き出して声を生み出すために、肺活量を鍛えて空気を吸い込む必要があるのです。
声量UPのために肺活量を増やす
人間の声帯を通る吐いた息が「声」とよばれることから、人間の吐いた息でこの「声」の音量も決まります。つまり、ほぼ同じような体型の人間であれば、肺活量が多い人のほうがより大きな声を出すことができるということです。
そのため、より大きな声量を求める人は、肺活量を鍛えて、より多くの息を吐き出せるようになる必要があります。
また、肺活量がUPすると、長いフレーズを息継ぎすることなしに歌い切ることができますし、何よりも一つの曲を最後まで余裕を持って歌い切ることができるようになります。
このように、合唱部の人にとって「声」という楽器を十分に使いこなすために、肺活量を増やす努力というのは常に必要なものなのです。
意外と重労働な「歌う」という作業
そして、忘れてはいけないことは、「歌う」ということは意外とカロリーを消費するハードな動作であるということです。
まず、合唱部で人が歌うとき、ほとんどの場合立って歌を歌います。その上、歌を歌っているときは体にある呼吸筋をフルに使っていますから、いわば立ったまま腹筋運動と背筋運動を同時にしているような状態になります。
その上、合唱をする人は指揮者の動きに常に注意を払っている必要があります。指揮者がどのような合図を出すか、常に集中していなくてはならないのです。
脳に十分な酸素が行き渡らないと人間は集中することができません。また、酸素不足の脳では、演奏中指揮者の出す指示に対して、合唱の人が即座に反応する事もできません。
このように、歌うということは意外とハードな動作で、脳や体が酸欠状態になった状態ではできないものなのです。
また、こうしたハードな歌うという動作をした後、人は疲労から回復する必要があります。しかし、酸素が脳にも全身にも十分に行き渡らない状態では、人間の疲労は回復するのに多くの時間が必要となります。歌うことによる疲労から回復するためにも、肺活量を多くしておくことは有効です。
このようなことがあるため、合唱をする人は、肺活量をきたえる必要があるのです。
吹奏楽をする人が肺活量を鍛えるメリットとは

では、もしも吹奏楽をしている人が肺活量を増やすことができたら、どのようなメリットがあるのでしょうか。
具体的にはつぎのような効果があるものと考えられます。
① ロングトーンが安定する
肺活量がアップすることが最も顕著に現れるのが、ロングトーンに対応できるようになることではないでしょうか。
息継ぎをする時間のない長いフレーズを演奏するときでも、最後まで安定した音色で演奏できるようになります。
また、特に伴奏のパートが多い管楽器はロングトーンに対応できるようになると、演奏中の存在感が一気に増加します。
② 表現の幅が広がる
担当している楽器によっては、高い音を演奏する時と低い音を演奏する時には、呼吸の仕方をそれぞれ変更する必要がある場合があります。
例えば、チューバをはじめとする金管楽器は、高い音を出すときには、低い音を出すときよりも、唇の振動回数を多くしなくてはなりません。
つまり、金管楽器は高い音を出す時には、唇をたくさん震えさせるために、より多くの空気を速いスピードで唇から入れる必要があるのです。
このため、肺活量が少ない人が’金管楽器を演奏する時は、高い音を出すことにかなり苦手意識を持っている人が少なくありません。
しかし、肺活量が増えるとより多くの空気を唇に通すことができるようになるので、高音が続いても安定して演奏できるようになるのです。
このため、高音への苦手意識がなくなり、演奏の幅が広がります。
③ 最後まで余裕を持って楽曲が演奏できるようになる
何よりも、肺活量があると、体力的に余裕ができて、曲を最後まで無事に演奏することができるようになります。
コンクールや演奏会などでは2~3曲を続けて演奏する必要がありますが、肺活量が上がると、1曲でヘロヘロにならずに、コンクールが終わるまでしっかりと演奏をすることができるようになります。
肺活量を鍛える方法【3選】

肺活量を鍛える方法としては次のような方法があります。
一日5分くらいで良いので、日常的に取り入れるようにすると、肺活量がアップして、音色が見違えるほど美しくなりますよ。
まずはリラックスから【呼吸筋マッサージ】
マッサージの気持ちよさは、みんなが知るところです。そして呼吸筋は24時間365日動き続けている筋肉なので、常に疲労している事が多いのです。そのため、呼吸筋を筋トレする前に、呼吸筋をマッサージすることを強くお勧めします。
呼吸筋をマッサージし始めると、特に横隔膜のあたりは触るだけ痛みを感じることがあるかもしれません。しかし、少しずつマッサージをするようになると、痛みも軽減しますので、諦めずにマッサージを続けてみましょう。
まず、最初に肋骨のあたりを手のひらで優しくさすってみましょう。その後できれば、肋骨の間に指を入れてマッサージします。そして最後に肋骨の下のあたりに指を入れてマッサージしましょう、肋骨の下には横隔膜があり、ここを直接マッサージすることで呼吸が楽になる人もいることでしょう。
最後に鎖骨のあたりも手のひらで円を描くようにマッサージしてみましょう。強い力を加える必要はないので、服の上から手のひらで優しくマッサージしてください。
演奏する前にこの呼吸筋マッサージをしておくと、肺活量も増えて、合唱でも吹奏楽でも音が出しやすくなるのでおすすめです。
【マスク生活での息苦しさを解消】肋間筋のマッサージを始めよう!
筋肉を伸ばして刺激を与える【呼吸筋ストレッチ】
実は吹奏楽や合唱をする人は、他の人以上に呼吸筋が疲労していることも多いもの。そして筋肉は疲労しすぎると傷ついたりしてダメージを負ってしまうもので、それは呼吸筋も例外ではありません。
そのため、吹奏楽や合唱ををする人は、日頃から意識して呼吸筋のストレッチをしていたほうが良いでしょう。
特に演奏前にはストレッチをして、呼吸筋をリラックスさせてから演奏すると音色が安定し、呼吸も楽にできるようになるでしょう。
呼吸筋のストレッチは、まず手のひらを胸の前で組み、深呼吸しながら前に突き出します。そして腕の中にボールを抱えているようなイメージで背中を軽く曲げて、深呼吸を数回繰り返します。
その後は、腰の後ろで手のひらを組み、グィと両腕を背中の上部方向へ持ち上げます。そしてそのままの状態で、数回深呼吸します。
この2種類のストレッチだけで、呼吸筋がしっかりと伸ばされ、血行が良くなり、肺活量がUPします。人によっては、体が暖かくなるのを感じられるかもしれません。
またストレッチ以外でも、日頃から意識的に胸やお腹の辺りを温めるだけでも、血行が良くなり、ストレッチと同じような効果があります。そのため、お風呂に入って体を温めることもおすすめです。
呼吸筋を鍛えるためのストレッチとは、どのようなもの? そしてその効果とは?
本格的に呼吸筋をきたえる【呼吸筋筋トレ】
吹奏楽や合唱部の人が演奏のために肺活量を鍛えようと思ったら、まず注目する必要があるのは横膈膜の動きです。演奏中は横膈膜を適切に動かして息を吐きだし、音を出す必要があります。
そのため、特に管楽器の演奏をする人は、横膈膜の動きを特に鍛えることが必要になります。
例えば、背筋をのばした状態で息を吸いながら両手を挙げ、その後息をゆっくりと吐き出しながら両手を下げることを繰り返しても、横膈膜を動かすトレーニングになります。
また、横隔膜以外の重要な呼吸筋として、腹直筋があります。いわゆる「腹筋」呼ばれるこの筋肉も呼吸筋の一部なのですが、この腹筋は特に息を吐き出すときに最も使う筋肉です。
吹奏楽も合唱も、音が出るのは、肺から空気が出たときだけです。そのため、この「腹筋」を鍛えてしっかりと息を吐き出すようになることで、しっかりした音色を出すことができるようになります。
そのため、吹奏楽や合唱をする人は、呼吸筋を鍛えておくのは必須と考えたほうが良いでしょう。
呼吸筋を筋トレ方法とはどのようなもの? 呼吸筋を鍛えると腹圧は上がる?
呼吸筋トレーニングデバイス「エアロフィット」を利用
また、「エアロフィット」のような呼吸筋をトレーニングする専用器具を使うことも、一つの方法です。
こうした器具を使って、毎日少しずつ呼吸筋をトレーニングすることも、肺活量アップに有効です。
エアロフィット・アクティブ / AIROFIT ACTIVE
肺活量を鍛えて、美しい音色を奏でよう

吹奏楽で管楽器や金管楽器を担当する人にとって、肺活量を鍛えることは、美しい音色を生み出すために必要です。
肺活量を増やすためには、肺自体を鍛える以外にも、肺を動かす呼吸筋を鍛えることも有効な方法になります。
呼吸筋を鍛えることで胸郭がより大きく広がり、同時に肺も大きく広がることで、肺活量が増えます。
また、呼吸筋を鍛えることで姿勢が良くなり、その結果肺活量が増えることもあります。
呼吸筋を鍛えて肺活量を増やし、美しい音色を奏でましょう。